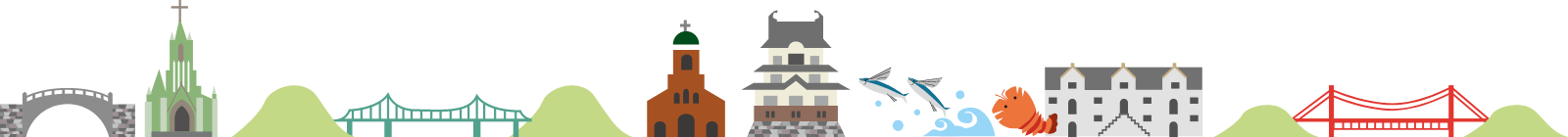乳幼児・児童の定期予防接種
定期予防接種(A類)
定期予防接種とは、予防接種法に定められているワクチン接種を、定められた期間(年齢)に行うことを指します。
平戸市では、法で定める定期予防接種(A類)として、ロタウイルス、B型肝炎、五種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ)、二種混合(ジフテリア、破傷風)、麻しん風しん混合、日本脳炎、BCG、小児用肺炎球菌、水痘、子宮頸がんワクチンの予防接種を指定医療機関における個別接種で行っており、接種費用については無料(全額公費負担)で実施しています。
乳幼児期の定期予防接種のご案内と予診票を、出生届けの際に保護者に配布しておりますので、お子さんの健康にお役立てください。
※里帰り出産等でやむなく長崎県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合には、接種費用の助成を受ける場合には、接種費用の助成を行っています。長崎県外で接種する予定がある方は、事前に申請が必要となりますので、下記までご連絡ください。
定期予防接種(A類)対象の感染症など
ヒブ
インフルエンザ菌、特にb型は、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの表在性感染症のほか、髄膜炎、敗血症、肺炎などの重篤な感染症を起こす病原細菌です。年間発症者数は約400人で、その過半数を生後4か月から1歳までの乳幼児が占めています。
小児肺炎球菌
肺炎球菌は、細菌による子どもの感染症の二大原因のひとつです。子どもの多くが鼻の奥に保菌しており、細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気を起こします。肺炎球菌による化膿性髄膜炎は年間150人前後が発症していると推計されており、死亡率や後遺症例(水頭症、難聴、精神発達遅滞など)はヒブによる髄膜炎より高いとされています。
B型肝炎
B型肝炎の感染症には一過性感染と持続感染の両方があります。免疫反応が不十分な時(新生児期など)に感染すると、ウイルスは肝細胞の中で長期にわたって生存する持続感染になり、将来、肝硬変から肝がんに進展する可能性があるため、注意が必要です。
ポリオ(急性灰白髄炎)
ポリオは「小児まひ」と呼ばれ、日本では1980年を最後に野性株ポリオウイルスによる患者の発生はなくなりましたが、海外から日本に野性ポリオウイルスが入ってくる可能性もあります。
ポリオウイルスに感染してもほとんどの場合は症状が出ませんが、感染した人のうち千人から二千人に1人の割合で手足のまひを起こす場合があり、一部の人にはまひが残ったり、症状が進行して呼吸困難により死亡することもあります。
百日せき
百日せき菌の飛沫感染で起こり、かぜに似た症状から続いてせきがひどくなり、連続的に咳き込むようになります。通常熱は出ませんが、乳幼児ではせきで呼吸ができず、けいれんが起こることがあります。肺炎や脳症などの重い合併症を起こし、命を落とすこともあります。
ジフテリア
ジフテリア菌の飛沫感染で起こり、発症後の症状は高熱、のどの痛み、せき、嘔吐などで、偽膜とよばれる膜ができて窒息死することもあります。発症後2週間から3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経まひを起こすことがあります。
破傷風
土の中にひそんでいる破傷風菌が傷口から体内に入り感染します。菌が体内で増えると菌の出す毒素により筋肉のけいれんが起こり、治療が遅れると死亡することもあります。
結核(BCG)
日本の結核患者数はかなり減少したものの、いまだ2万人を超える患者が毎年発生しており、大人から子どもへ感染することも少なくありません。
また、結核に対する免疫は母体からもらうことができないので、生まれたばかりの赤ちゃんもかかる心配があります。乳幼児は結核に対する抵抗力が弱いので、全身性の結核症にかかったり、結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残す可能性があります。
麻しん(はしか)
麻しんウイルスの空気感染によって起こり、感染力が強いため予防接種を受けていないと多くの人が感染する病気です。主な症状は、発熱、せき、鼻汁、目やに、発疹です。気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症も引き起こし、数千人に1人の割合で死亡します。
風しん
風しんウイルスの飛沫感染によって起こり、軽いかぜ症状から発しん、発熱、後頸部リンパ節の腫れなどが発症します。合併症として関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などがあり、大人になってかかると重症化します。
妊婦が妊娠早期にかかると、先天性風疹症候群と呼ばれる病気により心臓病、白内障、聴力障害を持った児が生まれる可能性が高くなります。
水痘(水ぼうそう)
水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、潜伏期間は感染から2週間程度です。発疹の前から発熱が認められ、一般的には、発疹は紅斑から始まり水疱、膿疱を経てかさぶたになり治癒します。日本では、年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。水痘は主に小児の病気で9歳以下での発症が90パーセント以上を占めると言われています。
日本脳炎
日本脳炎ウイルスの感染で起こり、7日から10日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を起こす急性脳炎になります。感染者のうち100人から10,000人に1人が脳炎を発症し、脳炎にかかったときの死亡率は約2割から4割で、神経の後遺症を残す人も多くいます。
子宮頸がん
子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。発生の多くは、ヒトパピローマウイルス(HPV:Human Papillomavirus)の感染が関連しているといわれています。HPVは性交渉で感染し、多くの場合、HPVに感染しても免疫によって排除されますが、HPVが排除されず感染が続くと、一部に子宮頸がんの前がん病変や、子宮頸がんが発生すると考えられています。
日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約2,900人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。 また、若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんで、患者数は20歳代から増え始め、30歳代までにがんの治療で 子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。
ワクチンを接種することで、HPVの感染を防ぎ、将来の子宮頸がんを予防できると期待されています。しかし、なかにはワクチンで防げないHPV感染もありますので、20歳以上の方は、2年に1回、子宮頸がん検診も受けることをおすすめします。
接種可能な医療機関
接種可能な医療機関はこちら
接種の際は、必ず医療機関に予約の連絡を入れ、母子健康手帳をお持ちください。
福祉部 こども未来課 母子保健班
電話:0950-22-9136
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)